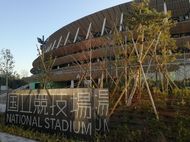もし東京オリンピックで、日本代表が6試合を勝ち抜いて金メダルを獲得するとしたら、それを見届けるのは誰だろう。無観客開催でないのなら、抽選でゴールドチケットが当たった少人数の幸運な人たち。あとはIOCなどの大会関係者、スポンサー企業の人たち。そして、取材パスを手に入れた報道関係者だ。日本ではオリンピックの取材パスはほとんどが「運動記者クラブ」に配分される。サッカージャーナリストがそれを手にすることはまずない。できることならサッカー競技限定で、日本サッカーの当事者でもある信頼できるジャーナリストたちが、その瞬間に立ち会って取材できればいいのだが――。
■「約束の料金を払ってほしい」
記事を送り、新聞社に電話を入れて記事が届いているか確認すると、1日の疲れもあって、私は夕食もとらず、シャワーも浴びずにベッドに倒れ伏してしまった。気がつくと、けたたましい音がする。部屋の電話だ。受話器を取ると、約束した例のタクシードライバーだった。彼は私のホテルは知っているし、私は名前も伝えてあった。「おれはあの場に行ったのに、お前は来なかった。約束の料金を払ってほしい」と言う。「ともかく部屋まできてほしい」と話した。
数分後、部屋のチャイムが鳴った。ドアを開けると、運転手が立っている。部屋まで押し掛けてきたと言っても、彼はけっして乱暴な感じはなかったし、どちらかと言えば疲れ切り、申し訳なさそうな顔をしている。「僕はあそこに行ったけど、あなたは来なかった」と言うと、「実は行けなかった。試合前にはあそこまではいれたが、試合後にはあの手前で止められてしまったんだ」。
それなら約束の料金を払う必要はない――。そう思ったとき、大柄な運転手の後ろから小柄な女性が顔を出した。彼の妻だった。けっして若くはない。夫同様、疲れ切った顔をしている。私は「ずるいよ~!」と心のなかで叫んだ。結局、約束の全額ではなかったが、行ったときと同様の額を払うはめになった。
おっと、こんな話を長々と書くつもりではなかった。2000年のシドニー・オリンピックでも、状況は同じだった。FIFAの広報担当には、前回と同じメールを送り、前回と同じ返事をもらっていた。キャンベラのスタジアムから同じフリーランスの後藤健生さんとバスで都心まで帰りながら、当時2人で『サッカー・マガジン』誌上で展開していた「対論連載」(このときだけは、2人分を一挙掲載という形だったと思う)の互いの内容を確認し合ったりして、ホテルに戻ると急いで原稿を書いた。