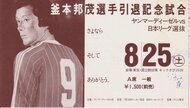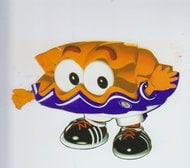サッカーは無数のディテール(詳細)であふれている。サッカージャーナリスト大住良之による、重箱の隅をつつくような超マニアックコラム。今回は日本サッカーの「夜明け前」。
■難しかった「プロ選手」としてのプレー
JSLで「プロ選手」が認められるのは、この2年後、1986年のことである。「オリンピック憲章」から「アマチュア」の文字が消されて12年、さまざまな競技でオリンピックのプロ選手が参加するようになっていた。ちょうどこの年、奥寺康彦さんが西ドイツのブンデスリーガでの9シーズンの活躍から帰国して古巣の古河電工(JSL)でプレーすることになった。体協の規定からようやく「アマチュア」の文字が外され、日本サッカー協会はプロ選手の登録を認め、奥寺さんと木村和司さんが「制約のないプロ活動」のできる「スペシャルライセンス・プレーヤー」として認定された。
それでも、JSLの中で公然とリーグ自体の「プロ化」が議論されるようになるのは、さらに2年後の1988年のことである。1984年9月、ロサリオのレプブリカ・ホテルのダイニングルームで私がマランゴニと向き合っていたとき、日本のサッカー界では「プロ化」などまだ想像もつかない時期だった。私はマランゴニにそうした日本の状況を説明し、プロ選手としてプレーすることは大変難しいと説明した。
「あなたの話は理解した。しかし、可能性のあるチームと話してみてくれないだろうか」
マランゴニは真摯だった。彼の穏やかな話しぶりと考え深い言葉の選び方には、高いインテリジェンスが感じられた。「日本でプレーしたい」という話が、思いつきや気まぐれではなく、さまざまなことを考えた末での言葉であったことがよく理解できた。
「わかりました。では、日本に帰ったら、トップリーグのクラブと話してみましょう」。私はそう約束した。